なぜ炭は燃え尽きてるのに燃えるのでしょうか?
少しだけ疑問に思ったことはあるけど、めんどくさがって目を背けていた炭の原理。
今回はその炭を納得できるまで調べました。
おまけにBBQで使われる理由も説明しています。
木材と炭の化学成分
まず、炭は木材等の植物からできています。木材と炭を比較することで、炭の理解が深まります。
木材の成分には、以下の物質が含まれます。
- セルロース
- ヘミセルロース
:
- 酸素
- 水素
- 炭素
:
- カリウム
- マグネシウム
- カルシウム
:
この木材が炭になったとき、構成される成分は
セルロースヘミセルロース
:
酸素水素- 炭素
:
- カリウム
- マグネシウム
- カルシウム
:
炭素と~ウムの物質(金属)だけになります。ーの傍線はガスとなり、炭には残っていません。
この間に何があったのでしょうか?
木材を普通に燃やしたときの仕組み

木材を密閉した容器の中(空気が少ない環境)で加熱することで、炭ができます。加熱するときに空気がたくさんあるかないかで、炭になるかどうか決まります。
はじめに、木材を空気がたくさんあるところで燃やしたとき、たとえば焚火をしたとき、木材はどうなるでしょうか?
木材は熱分解により、水蒸気といった不燃性のガスと、メタン、エタンといった可燃性ガスが出ます(揮発)。この揮発したガスが煙として現れます。
また、酸素と炭素が結びつき二酸化炭素となり大気に放出します。
$ C + O_2 → CO_2 $
木材がきれいに燃え切ったとき、残るものは灰です。
灰の正体は前の章で出てきた”~ウムの物質(金属)”です。金属は燃えることなく、そのままの状態か酸化した状態。つまり固体として最後まで残ります。
木材を大気中で加熱すると灰になる これを燃焼といいます。
炭ができる仕組み

では、木材を密閉した容器の中(空気が少ない環境)で加熱したときは、どうなるでしょうか?
空気がたくさんあるときと同じように、熱分解によりガスが出てきます。
可燃性ガスは出ますが、今回は酸素が少ないので、炎が起こりません。
そして酸素が少ないので、木材中の炭素は二酸化炭素になれず、固体のままです。
よって、熱分解によるガスが出尽くした後、容器の中には炭素と金属の固体が残ります。
これが炭の正体です。
炭を空気がたくさんあるところで燃やすと、木材と同様に灰になります。
木材を密閉容器内で加熱すると炭になる これを炭化といいます。
こうしてできた炭は木材だったときの骨格(組織)を保ち、微細な孔を無数に持つ多孔質な状態になります。よって、炭の中には酸素が入りやすく安定した燃焼を可能にします。
上質な炭を燃やすと、二酸化炭素が放出されるだけです。よって燃やしても、煙は見えず、匂いもありません。
灰の小話
木炭の灰に含まれているカリウムが植物にとってうれしい肥料になるそうです。
もし、キャンプ場等で炭は灰の捨て場所が設置されてない時、そのまま捨てて帰ると景観を一方的に汚してしまいます。
きれいなキャンプ場を維持するためにも、炭や薪はなるべく完全燃焼させます。残った灰は地中に埋め、埋めた場所に十分な水を撒くと良いそうです。
景観も保たれ、森林の肥料にもなります。もちろんしっかり鎮火されてることが愛前提です。
おまけ:BBQに炭を使う理由

鉄板より炭火でお肉を焼く方がなぜ、おいしいといわれるのでしょうか?
それは、炭火の方が短時間で加熱することできるからです。
鉄板の場合
高温の鉄板がお肉に直接触れることで、熱が鉄板からお肉に伝わります。鉄板から熱をもらったお肉が徐々に焼けていきます。
炭火の場合
熱の伝わり方が2種類あります。
1つ目
まず鉄板と同じ原理で、炭火に直接触れた空気が熱くなります。次に、熱くなった空気がお肉に直接触れ、お肉が徐々に焼けていきます。
2つ目
炭は熱を持つと、強い遠赤外線(電磁波の1種)を放出する性質を持ちます。また、動植物は遠赤外線を受けとり熱として吸収される性質を持ちます。こうして、お肉が焼けていきます。
炭火の場合、2つ目の遠赤外線による加熱が優れており、お肉を短時間で焼くことができます。
お肉を短時間で焼くことができるので、表面がカリカリに焼けて、中の肉汁を逃がしません。よって、おいしく焼けます。
本当に簡単に説明しましたが、電磁波は身の回りにあふれてます。電磁波は面白い分野なので何かの記事で取りあげれたらと思います。
まとめ
今回は木炭ができる仕組みを説明しました。まとめると…
- 木を空気が少ないところで加熱することで炭(炭素+金属)となる。
- 木を空気があるところで燃やすと灰(金属)となる。
- 上質な炭を燃やすと、二酸化炭素(透明なガス)のみが放出される
- 炭を燃やすと同様に灰になる
原理を分かって使うと、いつもと違う楽しみができると思います。今回のように気になったことは調べて、報告していけたらと思います。
参考文献
“炭の力”, 杉浦銀治 監修, 炭活用研究会 編著
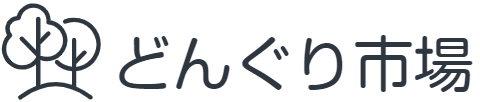


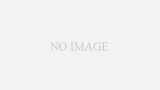
コメント